創刊1号の読みものとして「ほぼ日」の代表である糸井重里に話を訊くことにしました。糸井がこの春を経て何を考えたのか、そして今後のほぼ日はどこへ向かうのか、率直に訊いてみました。
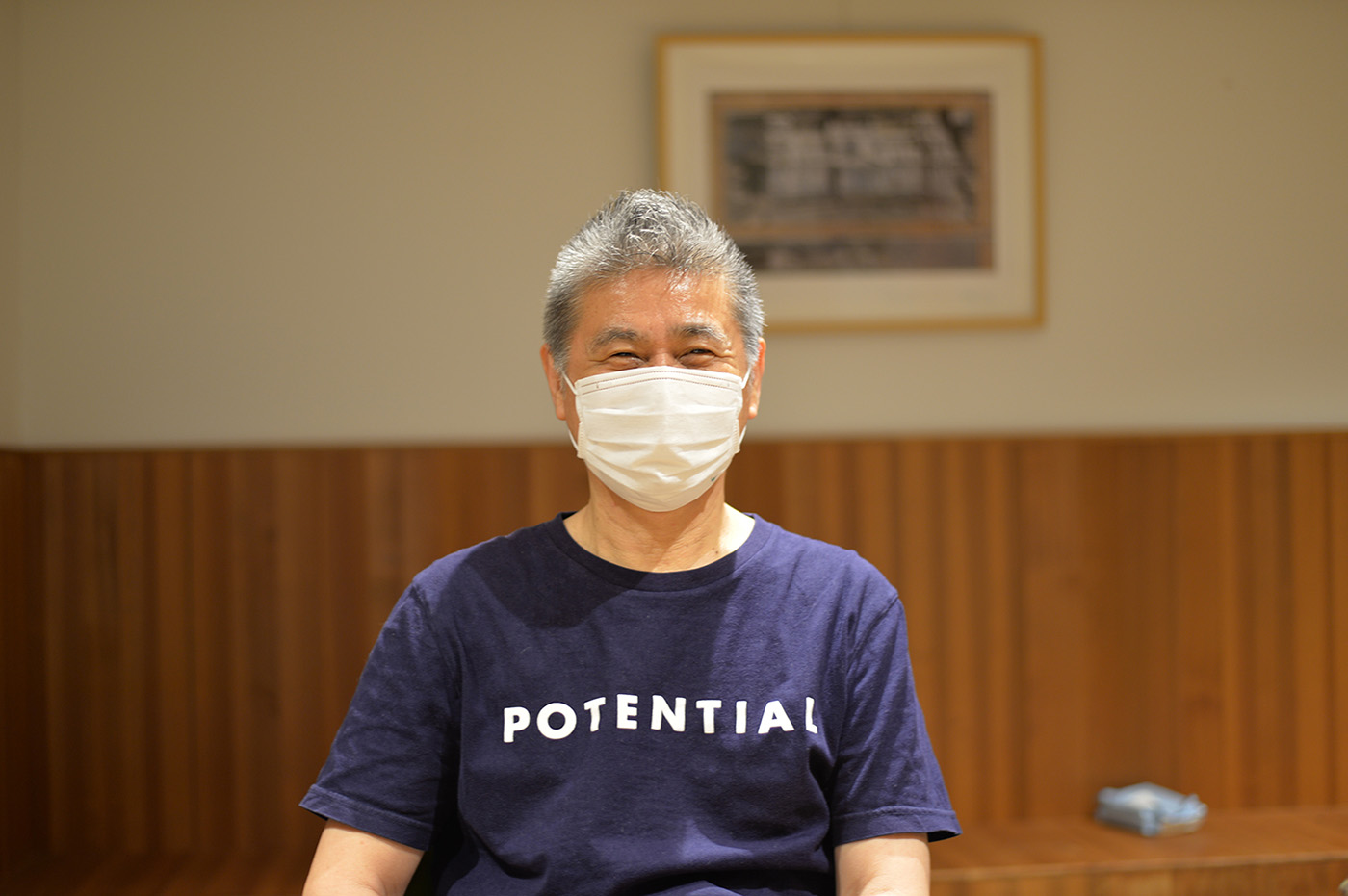
――:
いま、新型コロナウイルスの影響から、社会が少しかたちを変えようとしているように感じます。「ほぼ日」は6月で創刊22周年を迎えましたが、これからの「ほぼ日」が進む道のりについて、どのように考えていますか?
糸井:ずーっと「同じなんだよなぁ」と思うことが、ぼくにはあります。
「ほぼ日」はWEBページというかたちを取っていますよね? それはメディアの一種です。プラットフォームというものは、つまり、インターネットもテレビもそうですが、すべて仕組みのことなんです。ぼくたちは仕組みを目の前にすると「そこには夢がある」と思い込みがちですね。
たとえば「テレビというものができたら、世の中変わっちゃうぞ」とかね? たしかに変わるけれども、それは車にとっての道のようなもので、ぼくたちがどんな車に乗りたいか、どこに行きたいか、ということには、じつはそれほど関係がありません。
仕組みをあまりもてはやさないようにしよう、仕組みそのものに惚れこまないようにしよう、と、つねに思ってきました。
「ほぼ日」は、いまもむかしもずっとホームページです。1998年に開設してしばらく経つと、ホームページからブログの時代になりました。当時はいろんな人から「なぜブログにしないんですか?」というアドバイスを受けましたが、いまはブログからSNSの時代に移りましたね。そうやって道具は変わっていきます。しかし、そこに「載るもの」は道具にはあまり関わりません。
ぼくたちが使う道具は、でっかい網かもしれないし、糸電話かもしれません。いっぺんに大勢の人びとに伝えることができるものかもしれないし、少なくひっそりと伝えるものかもしれません。この、あたらしくはじめるメールマガジンもそうでしょう。「お皿部分」はなんでもいいんです。
そこで、あなたは、私は、何を言いますか?
「もしもし」と言うのか?
「おまえが好きだ」と言うのか?
「ラーメン食べたい」と言うのか?
「ラーメンにちょっと胡椒ふるとおいしいよね」って言うのか(笑)?
けっきょく我々「人」が、そこで何を思ったか。仕組みの上に載っかっているものがいちばん大事なのです。
忠臣蔵の歌舞伎も、紙切れに書いた「I LOVE YOU」も、すべてが同じ「コンテンツ」です。人が考えた「跡」が、すべての物語、すべての表現に入っています。人がおもしろがるもの、自分が興味があるもの、すべてそこです。「ほぼ日」は22年前から変わらず、そこのところをいつでも得意でありたいと思っています。
ウイルスの影響で不便になったり、リモートワークや時差通勤が快適だったり、いろんなことがあります。けれども、そこで自分たちが何を話してどう思ったのか? どのような状況にあっても、そこが大切です。
(糸井へのインタビュー、次週につづきます。次週はほぼ日の本社とセットになって神田に大移動する「ほぼ日の学校」について。そうなんです、ほぼ日は神田に引っ越します。どうぞ次の記事におすすみください)